工芸品
国指定重要文化財
古備前筒大花生

戦国時代に作られたもので、高さ38センチメートル、口径15センチメートル、胴部に「備州大滝山中道院常住物弘治三年三月廿一日」の刻銘がある。制作年代が銘から確定でき、備前焼研究上重要な作品である。
裾がやや広がった筒型の器形で、表面は縦横に箆目を施し、半面のみ自然釉がかかっている。桃山時代に入る直前に生産されており、生活雑器から美術工芸品への脱却を試みようとする制作者の意図が感じられる。
(補足)弘治3年:1557年
- 登録日 昭和31年6月28日
- 所在地 和気(岡山県立博物館寄託)
- 見学 不可
銅五鈷鈴

天台宗派の寺院である安養寺に伝わる銅製の鈴で、天台密教の修法を行うときに鳴らして用いる法具である。錮が五つであることから五錮鈴と呼ぶ。
「備前国新田安養寺了円之建武五季三月日」との刻銘があり、建武5(1338)年に制作されたものとわかる。
「建武」は北朝の年号であり、了円は、足利氏率いる北朝方についた赤松円心の従弟といわれ、寺にはこの五錮鈴を使って了円が北朝の安泰を祈願したと伝わっている。
- 登録日 昭和34年12月18日
- 所在地 和気町泉
- 見学 不可
県指定重要文化財
備前焼薄端花生

戦国時代に作られた薄端式の花生で、無銘である。総高34.5センチメートル、外口径37センチメートル、内口径9.1センチメートル、高台径14センチメートル。
大きさから寺院に供える花のための花生と思われる。孔と鉤が両耳に付き、均整のとれた端正な形が優れている。茶道、華道が枯淡さを求める室町時代以降の文化に対応し始めた頃の備前焼としては最古級のものと言われている。
(注意)写真は「和気町町制施行50周年記念町勢要覧2003」より引用。
- 登録日 昭和34年3月27日
- 所在地 和気町駅前
- 見学 不可
陣太鼓

胴部はケヤキ、牛革張りで、革張り部の直径53センチメートル、胴の奥行き42センチメートルである。室町時代初期から室町時代中期の間の作で、県内に現存する最古の太鼓とされる。
革部は中心に左回りの三つ巴文、周囲に矢車文を表現し、縁に宝相華文が描かれる。後世の補修などがほとんど入っておらず、制作当初の形態を残している点で貴重。赤松則村(円心)が使用したとの伝承を持つ。
- 登録日 平成15年3月11日
- 所在地 泉(岡山県立博物館寄託)
- 見学 不可
由加神社宝物(赤松則祐の鎧)

この紺糸素懸威胴丸具足は、赤松則祐が着用したと伝わる。「胴丸」の特徴を持ちながら、「具足」の要素も備えている。戦国時代の作と考えられる。
- 登録日 昭和32年1月23日
- 所在地 大田原
- 見学 不可
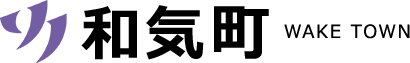




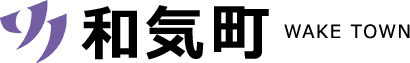




更新日:2024年03月18日