建造物
国指定重要文化財
旧大國家住宅

大國家は江戸時代後期、運送業と酒造業などを営んだ。主屋・蔵座敷・中蔵・乾蔵・酉蔵・井戸場の6棟と附属土塀からなる。
宝暦10(1760)年新築の主屋は、約18メートル四方のほぼ正方形の平面構造をしており、2つの入母屋造の茅葺屋根の中央部分を切妻造の瓦葺屋根で連結する「比翼入母屋造」である。これは全国的にみても珍しく、吉備津神社本殿(岡山市)など数例が見られるのみで、民家建築としては唯一ではないかと言われている。
- 登録日:平成16年7月16日
- 所在地:尺所
- 見学:不可
- 注意事項:改修工事のため。見学会開催の場合は和気町ホームページ内にて告知します。
登録有形文化財
「登録有形文化財」とは
保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、指定文化財制度よりもゆるやかな規制のもと保存していこうという「文化財登録制度」が平成8年10月1日から導入されました。築50年を経た歴史的建造物で、一定の評価基準に達していれば、「登録有形文化財」として認められます。登録有形文化財は、外観を変えなければある程度自由に活用し、利用することができる点で”ゆるやか”であるといえます。
和気町では、現在3件の建造物が登録有形文化財となっています。
佐伯町ふる里会館

昭和7(1932)年に完成した鉄筋コンクリート造の初期の建物である。旧山田村役場としてつくられ、外観は左右対称とし庁舎の風格をもたせている。外柱や正面2階窓に意匠をこらしている。
- 登録日:平成9年9月1日
- 所在地:岩戸
- 見学:可
- 注意事項:ただし事前に問い合わせが必要です。
万代家住宅主屋

明治5(1872)年の建築で、入母屋造の屋根を持つ。小屋組みに、釿(ちょうな)削りの丸太を複雑に組み合わせており、大工技術の高さを示す。
- 登録日:平成11年7月8日
- 所在地:原
- 見学:不可
永井家住宅主屋

木造の歯科診療所兼住宅である。大正5(1916)年に新築されたという。当時東備地域には洋風建築は珍しく、時代の先端をいく建物であった。
- 登録日:平成12年4月28日
- 所在地:和気
- 見学:不可
- 注意事項:外観のみ見学可
県指定重要文化財
石造密厳寺五重層塔

この層塔は大王山密厳寺跡にあったものを天明4(1784)年に本久寺住僧・日勧が現在地へ移したものである。密厳寺は、本久寺の前身と言われる真言宗の寺院で、天正11(1583)年に浮田土佐守が密厳寺の諸堂宇の一部を遷して本久寺を開いたとされる。
別石で造られた塔身、笠ともに花崗岩製で、高さは2.8メートル、側面に「元享四年甲子二月二十二日」の銘が刻まれている。(補足)元享4年:1324年
- 登録日:昭和33年4月10日
- 所在地:佐伯
- 見学:可
石造密厳寺九重層塔

この層塔は大王山密厳寺跡(和気町米沢)にあったものを大正2(1913)年に現在地へ移したものである。
塔身、笠はともに花崗岩製で一つの材を加工して造られており、高さは6.75メートル、側面に「元享二年壬戌八月六日」の銘が刻まれている。上部の相輪が失われており、宝篋印塔を載せている。(補足)元享2年:1322年
- 登録日:昭和33年4月10日
- 所在地:佐伯
- 見学:可
石造長楽寺五輪塔

杉沢山長楽寺跡(和気町田土)の門前にあたる丘に建つ、南北朝時代のものである。
花崗岩製で、高さは1.55メートル、塔身に「融通経象敬白貞治五年丙午二月日」との銘があり、四方に梵字が薬研彫で刻まれている。(補足)貞治5年:1366年
- 登録日:昭和34年3月27日
- 所在地:田土
- 見学:可
本久寺本堂

熱心な日蓮宗徒であったと伝えられる浮田土佐守が、天正9(1581)年に起工し、同11(1583)年に完成した。大王山にあった密厳寺の諸堂宇の一部を中心に新たに建てたものである。棟札より慶安4(1648)年に大修理が行われたことがわかっているが、創建当時の豪壮な桃山建築の特色をのこす。
桁行5間、梁間6間、本瓦葺の入母屋造りで、正面と背面に向背がつく。
- 登録日:昭和34年1月13日
- 所在地:佐伯
- 見学:不可
- 注意事項:外観のみ見学可
町指定重要文化財
善照寺石造九重層塔

善照寺の住僧が還俗した後に、善照寺境内から現在地の矢田八幡神社境内に移したものである。花崗岩製で塔身は2.04メートル、室町時代の作と考えられる。上二層が欠損しているが、美麗である。
- 登録日:昭和48年3月1日
- 所在地:矢田
- 見学:可
宝篋印塔

花崗岩製で、塔身の四方に梵字を刻み、細密で装飾性に富んだ造りである。
室町時代の作と考えられる。
付近に石積1基があり、「大方古墓」として遺跡になっている。
- 登録日:平成元年5月26日
- 所在地:奥塩田
- 見学:可
法泉寺本堂

法泉寺本堂は、明治11(1878)年に「第10番教会所」として建てられた。日本建築の技術や材を使いながら随所に洋風の造作が見られる擬似洋風建築となっている。
(注意)法泉寺本堂の見学には紹介者が必要です。
- 登録日:昭和51年4月1日
- 所在地:益原
- 見学:不可
- 注意事項:外観のみ見学可
本成寺本堂

本成寺は慶長6(1601)年に開かれた顕本法華宗の寺院である。天井絵をはじめ極彩色で彩られた内装と、華やかな彫刻をもち豪壮な桃山建築の特徴が随所に見られる。
- 登録日:昭和51年4月1日
- 所在地:和気
- 見学:不可
- 注意事項:外観のみ見学可
和気神社本殿


鐸石別命や和気清麻呂、応神天皇を祀る。木造、一間社流れ造。明治18(1885)年に田淵勝義によるものである。飾彫刻が江戸時代後期の装飾主義の影響を示している。
- 登録日:平成10年9月10日
- 所在地:藤野
- 見学:不可
- 注意事項:外観のみ見学可
法泉寺題目石

備前(岡山)地方にはじめて日蓮宗(法華宗)を伝えた大覚大僧正が、依頼を受けて書いたものと伝えられている。塔身の三方に、「南無妙法蓮華経」の文字が刻まれている。
(注意)法泉寺題目石の見学には紹介者が必要です。
- 登録日:平成11年8月10日
- 所在地:益原
- 見学:不可
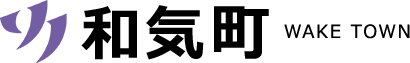




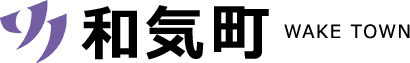




更新日:2024年03月18日