火災
緊急時の対応
お問い合わせ先
火災防止10か条
今まで何も起こらなかったからといって、明日も大丈夫という保証はありません。
あなたの生活習慣を見直して、防火意識の高い新しい習慣を身につけましょう。
1.ストーブの周辺はすっきりと
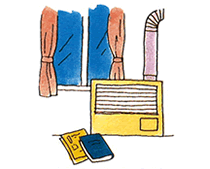
特にカーテン、洗濯物には要注意。石油ストーブの給油、移動は必ず火を消してから。
2.揚げ物のときはその場を離れない
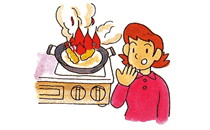
電話や来客の応対は、必ず火を消してから。
そばに燃えやすいものを置かない心掛けも。
3.寝たばこ、ポイ捨て厳禁
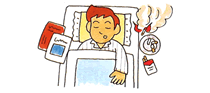
寝たばこは、しない、させない習慣を。火のついたたばこの放置やポイ捨ても厳禁。
4.放火させない環境づくり
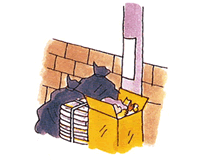
家の回りに燃えやすいものを置かない。物置、車庫などのカギはしっかりと。
5.強風の日のたき火は危険

消火用の水を用意して。子どもだけでたき火をさせない。風のある日のたき火は中止。
6.子どもにはマッチやライターで遊ばせない

日頃のしつけをしっかりと。目の届くところにマッチやライターを置きっぱなしにしない。
7.風呂の空だきをしない

点火のときは浴そうの水量を確かめて。点火、消化は目で確認。
8.コンセントにこまめな気づかい
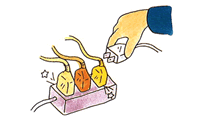
たこ足配線、コンセントまわりのホコリに注意。使わない時はこまめに抜く。
9.就寝前の火の用心
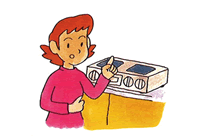
ガスの元栓、コタツのコンセントなど指さし点検で火の元確認。
10.消化の備えを万全に
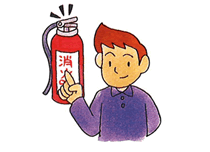
簡易型火災警報機や消化器を設置して防火訓練には積極参加。
火災が起きたとき
- 天井に火が燃え移ったときが避難の目安
- 服装にこだわらない。ただし化繊などの燃えやすい素材のものは気を付ける。
- 貴重品に執着しない。ひとまとめにしておいて、いざというときに持ち出す。
- 火の中は一気に走り抜ける。足元に注意。
- 煙の中では姿勢は低く、床をはうように。室内は壁づたい、廊下なら中央を進む。
- 濡れタオルで口をふさいで煙を避ける。
- お年寄り、子ども、病人を最優先に。
- いったん逃げ出したら、再び中には戻らない。
- 大声を出して近所に知らせる。
- 逃げ遅れた人がいるときは、すぐに消防隊員に知らせる。
対処方法
- まず大声で知らせる
- 「火事だ~!」と大声を出し、家族や近所に知らせる。
- 小さな火でも119番。当事者は消火にあたり、近くの人に通報を頼む。
- 早く消火する
- 出火から5分以内が消火できる限界。
- 水や消化器だけでなく、座ぶとんでたたく、ふとんをかぶせて密閉するなど機転をきかせて消火にあたる。
- 早く逃げる
- 天井に火が燃え移ったらあきらめてすぐ避難。
- 避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉めて。
- 消化器がない場合は、ぬれたシーツなどを広げて火元全体を包み、空気を遮断する。
- 煙の中を逃げるときはできるだけ姿勢を低くして。濡れタオルで口をおおうなどして煙をさける。
- ぬらしたタオルなどで顔や体をおおう。炎の中は一気に走り抜ける。
- 逃げ遅れた人がいるときは、近くの消防隊にすぐ知らせる。
- いったん外へ逃げたら再び中には戻らない。
- 避難は、お年寄り、子ども、病人を最優先。
- 天井に燃え移ったらもう手に負えない。消火の深追いをしないで、いさぎよくあきらめて避難する。
- ふすまや障子戸は思いきりけり倒し、低い位置で消火。
- カーテンは力いっぱい引きずりおろし、天井へ火が燃え移らないようにする。
- 「火事だ~!」の声を聞いたらすぐ119番通報。誰かが通報しているだろうと考えず、ダブっても良いからとっさにダイヤルを。
- 服装や持ち物にこだわらず、できるだけ早く避難する。
火の消し方
- 油鍋
水をかけない。元栓を閉め、大きなふたをして空気を断つか、シーツなどを濡らして手前からかける。 - 石油ストーブ
濡らした毛布などをかぶせ、その上から一気に水をかける。 - 電気製品
いきなり水をかけると感電のおそれがあります。プラグを抜き(できればブレーカーも切り)消火。 - 風呂場
急に開けると空気が補充され、火勢が強くなるので、ガスの元栓を閉め、徐々に戸を開けて一気に消火。 - 衣類
床や地面をころげ回り火を消す。すぐ脱げるものは、脱いで足を踏み出す。 - カーテン・ふすま
出火して2分前後で立ち上がり面に燃え移る。 天井には火が回る前にカーテンは引きちぎり、ふすまはけり倒して消火。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課くらし安全係
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1123
お問い合わせはこちら
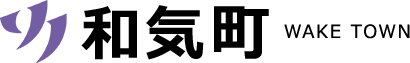




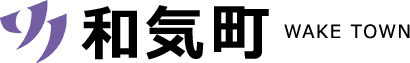




更新日:2024年03月18日