介護保険認定・更新認定・区分変更認定申請について
介護保険サービスを利用するには、町に要介護認定の申請をしていただき、要介護度の認定を受ける必要があります。申請は、役場介護保険課で受け付けています。
町では、申請を受けると調査員が申請者のお宅等を訪問して、全国共通の項目内容について聞き取り調査を行い、この調査と主治医意見書に基づき、コンピュータによる一次判定が行われます。この一次判定の結果と主治医意見書、調査の特記事項を基に、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会で審査・判定を行い、要介護度が決まります。介護が必要になった時、もしくはすでに認定を受けている方が更新する場合や、体調の変化などによる認定の内容変更する場合には、申請を行ってください。
本人が申請できない場合は、代理申請ができます。
要介護・要支援とは
要介護や要支援とは、介護保険サービスを利用する基準となるものです。訪問介護やデイサービス、福祉用具貸与、住宅改修などの介護保険サービスを利用する際に、まずどれぐらいサービスが必要な状態なのかを判断するために要介護認定を受けます。
要介護・要支援認定を受けられるのは、65歳以上または40歳以上で要介護状態が特定疾病(16疾病)に基づく方です。
町から要支援1、2または要介護1~5と認定を受けると、介護保険サービスを利用することができます。
自立(非該当)と判断されると、介護保険サービスを利用することはできません。
要支援とは
身体または認知症などの精神の障害があり、状態の軽減や悪化の防止のために介護予防サービスが必要な状態です。要支援には1と2があります。
要支援1、2では、町が提供している介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)にて訪問介護や通所介護等の介護予防サービスを利用することが可能です。
要介護とは
身体または認知症などの精神の障害があるため、日常生活における基本的な動作において、継続して介護が必要な状態です。要介護には1~5の5段階があります。要介護1はもっとも要支援に近く、要介護5は最も介護が必要な状態です。
要介護1~5では、介護保険が適用される老人保健施設や介護療養型医療施設などの介護保険施設に入居などの介護サービスを利用することができます。
介護サービス利用までの流れ
1.相談・申請
本人または家族などが和気町役場介護保険課で「要介護認定」の申請をします。地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。
必要な書類は次のとおり
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
- かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
- 40歳から64歳で医療保険に加入している「第2号被保険者」の方は、加入している医療保険の保険証
介護保険認定・更新認定・区分変更認定申請 (Wordファイル: 12.3KB)
認定・更新・区分変更申請書(表・裏) (PDFファイル: 125.8KB)
認定・更新・区分変更申請書(表・裏) (Wordファイル: 20.7KB)
2.認定調査
事前に役場介護保険課職員や委託事業者から連絡の上、調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
調査員は町職員や事業者等に所属する認定調査員となります。
3.主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。心身の障害の原因である疾病等の状況を記載します。
4.要介護認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
介護認定審査会の審査・判定に基づき、町が要介護度の認定を行います。
5.居宅介護支援事業者等への相談
介護が必要と認定された方(要介護1~5)は、居宅介護支援事業者と相談し、介護サービス利用を開始します。
支援が必要とされた方(要支援1・2)は、地域包括支援センターと相談し、介護予防サービス利用を開始します。
要介護認定の取下げについて
要介護(要支援)認定の有効期間中に、状態が改善した等の事情により、介護サービスを利用する予定がなくなるなど認定自体が不要となった場合は、認定の取下げ手続きを行ってください。
認定取下げ申請方法
認定の取下げを希望される場合には、介護保険認定申請取下書に必要事項を記入の上、介護保険被保険者証と合わせて、役場介護保険課に提出してください。
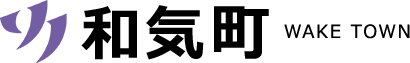




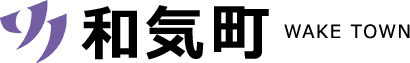




更新日:2024年03月18日